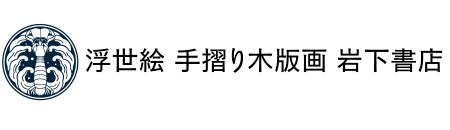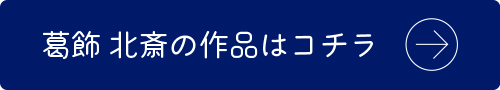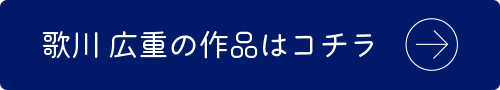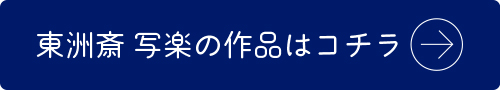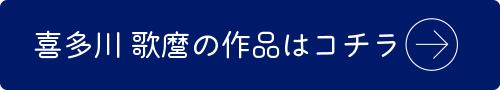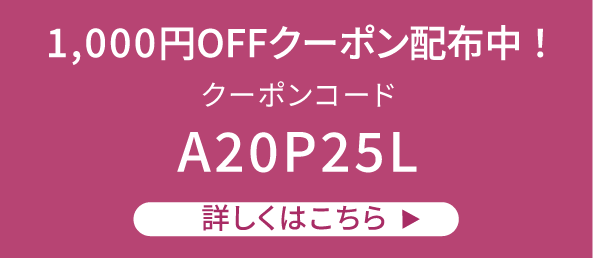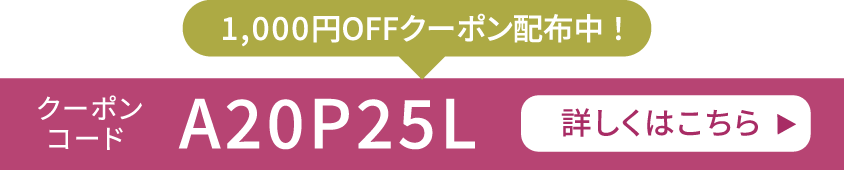摺の技術の一つ、『一文字ぼかし(いちもんじぼかし)』とは?
浮世絵木版画の摺りの技法に「ぼかし」があります。
版木のぼかしたい部分を水を含ませた布や刷毛で濡らし、
その上に絵具をおいて、
にじんだところを紙に摺りとるという技法です。
「一文字ぼかし」は、版木の上端に水平で真っ直ぐなぼかしを入れ、
主に空を表現するもので、天ぼかしともいいます。
上から下へ徐々に色が薄くなり、
自然なグラデーションを描くことができます。
効果としては絵に奥行き感とメリハリをつけ、
色で季節や時間、天候なども表現できます。
藍ならば晴天、昼間。
朱で秋、朝焼け、夕刻。
墨では冬、雪、雨、夜、といった具合です。
歌川広重の東海道五十三次には、
幅が狭くシャープな一文字ぼかしが多く見られます。

「日本橋 朝之景」では地平線上に朱をおき、
天に藍の一文字ぼかしをすることで、
朝焼けの残るよく晴れた朝の光景だとわかります。

「御油 旅人留女」では墨の一文字ぼかしで夜とわかり、
最後のチャンスとばかりにお客の争奪戦を
繰り広げる様がユーモラスに表現されています。
このように一文字ぼかしという技法は、
浮世絵木版画の風景画において、
作者と鑑賞者の間で
記号的な使われ方をしていたとも考えられます。
浮世絵木版画を見るときは上端の色にも注目してみてはいかがでしょう。